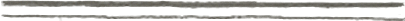ベートーヴェン交響曲第5番「運命」は なぜハ短調か
交響曲第5番ハ短調 C 午
ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」はなぜハ短調なのだろうか。ベートーヴェンはなぜ5番をハ短調に決めたのだろうか。作曲家というものはピアノに向かい鍵盤に指を乗せる前からキーの流れが頭をよぎっているはずである。調性やメロディーは構築するというやり方なのか、それとも自然に頭に浮かんでくるというようなものなのだろうか。それはおそらく作曲者が元々持っている波動に強く影響を受けているのではないだろうか。
ベートーヴェンの生まれは1770年12月。本命は寅の五黄土星。月命は子の一白水星となる。気学ではこの生まれを離宮傾斜と言い、行動パターン、思考パターン、生き方が離宮すなわち理念、理想、真理探究に傾いていく。この傾斜に属する人は、理想を追求するあまり、生活感覚、現実感覚に乏しく、地に足が付かない生き方となりがちである。ベートーヴェンはまさに離宮傾斜そのものの生き方をした偉人と言えよう。またそのような生き方でなければ、彼のような傑出した音楽は作れなかったであろう。
5番「運命」のハ(C)は十二支の午に当たる。午はベートーヴェンの本命寅(G♯)の三合音となり、ベートーヴェンにとって最も強く共鳴する音の一つとなる。Aを440Hzとするとハ(C)の一つの周波数は523Hzとなる。この場合Aを444HzにするとCはソルフェジオ周波数の528Hzとなる。528Hzを午の中心点の周波数とすると、528Hzには天性、神聖、真善美という意味合いが出てくる。午は後天図という気の配置図の中で頂点(南天)に配置される。これを離宮(りきゅう)という。離宮は天を表し、真理、正誤の判断を司る。つまりCという音には元来天運、命運を明らかにする意味がある。
♦
5という数にも「運命」にまつわる気学的な意味がある。5という数命には命運を発揮させる特別なエネルギーが備わる。さらに5は九星における五黄土星に当たる。五黄はエネルギーの発生を表し、自他ともに運気を激しく揺さぶる。故にその運気には成就と破綻の双方が現れる。5及びハ(午)が命運の現れを意味するなら、5番は成就と破綻の命運を表したと考えられる。
さらに重要な数である7についても言及しておきたい。交響曲第7番の調性はイ長調である。イ(A)は卯に該当し、卯の持つ自由奔放さが曲調に現れる。卯は後天図の震宮に当たり、震宮には音、振動、自由空間の意味がある。気学には1・4・7・10の法則というものがある。3のリズムで運気は展開し、7か月目、7年目で運気の流れが変化、逆転するという法則である。この流れから捉えると、交響曲7番には命運の転換、逆転という意味も加わるかもしれない。
気学では5番目に現れるエネルギー、7番目に現れるエネルギーそれぞれに意味がある。5は命運の決定、成就。7は命運の転換、逆転である。作為がないかぎり、ものごとは気の法則通りに動いていく。5番目に現れる作品、7番目に現れる作品の意味は偶然ではなく必然的に現れる。
ベートーヴェンの本命である寅の五黄土星は激しい気性と激しい運気の動きを持つ代表的命運。月命子の一白水星は精神的浮き沈みが多く、個性的であると同時に特異性を持つ命運。この二つの命運が重なり、真善美を追究する離宮傾斜を持つ。現実離れした創作力、音を通した真理探究のエネルギーは何よりもベートーヴェンが生まれながらに持つ本命月命から生まれている。
♦
【備考】
交響曲第5番
第1楽章ハ短調、第2楽章変イ長調、第3楽章ハ短調、第4楽章ハ長調
交響曲第7番
第1楽章イ長調、第2楽章イ短調、第3楽章ヘ長調、第4楽章イ長調
ベートーヴェンの本命寅(変イ)と三合は午(ハ)と戌(ホ)。楽章が三合音で繋がれていることに注目したい。7番におけるイ(卯)とへ(亥)も三合音。ベートーヴェンが調性の選択において、響きの調和と連続性を意識していたことが伺える。
ベートーヴェンの下記の代表作もハ短調、ハ長調である。ここでも楽章が寅・午・戌(変イ・ハ・ホ)の三合音で繋がれている。
ピアノ協奏曲第1番
第1楽章ハ長調、第2楽章変イ長調、第3楽章ハ長調
ピアノ協奏曲第3番
第1楽章ハ短調、第2楽章ホ長調、第3楽章ハ短調~ハ長調
ピアノソナタ第8番『悲愴』
第1楽章ハ短調、第2楽章変イ長調、第3楽章ハ短調
(浅沼気学岡山鑑定所監修)