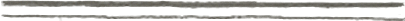カリウム Potassium K
カリウムは三碧木星の特徴である起爆力とエネルギー的要素を持つ元素である。三碧木星は一白水星とともに代謝に最も大きな影響を及ぼす。三碧と一白は非常に緊密な関係にあるが、三碧が中宮に同会すると一白は震宮に同会して暗剣殺という不安定化したエネルギーを伴う。震宮に同会する一白の役割は三碧の成長促進と制御である。三碧と一白の関係はプラス面とマイナス面があり、強い反応性を持つだけに代謝も陰に陽に揺さぶられる。
カリウムは生体においてナトリウムと拮抗する性質を持つ。ナトリウムは六白金星または一白水星の気質を持つため、カリウムを三碧木星の気質と見なすと、六白のナトリウムとは相剋の関係となり、一白の気質においては制御関係となる。
カリウムはタンパク質の合成、細胞における浸透圧の調整、酸と塩基のバランス、神経伝達、心臓・筋肉の動き、酵素反応の調整、生命維持のためのシグナル伝達など様々な働きを担う。これらの働きや症状は震宮の一白水星の働きからもたらされるものと考える。
〔金属カリウム〕
金属カリウムは水と爆発的に反応し発火する。これは三碧木星(カリウム)と一白水星(水)の関係性を物語る。震宮は外界に無条件で接する状態にあり、三碧が中宮にある時一白は震宮に同会して反応性が高まる。気学ではこれを暗剣殺とし、一白のプラスマイナス双方の気質が現れる。
〔浸透圧〕
カリウムは浸透圧を決定する主要因子である。カリウムを三碧木星とすると三碧中宮による震宮の一白水星は浸透圧調整の形と見ることができる。
〔血圧下降〕
ナトリウム(六白金星)は血圧を上昇させ、カリウムはナトリウムの排泄を促進し血圧を下げる。三碧木星と六白金星は相剋の関係で勢力が拮抗する。また三碧木星の力が増すと一白水星は暗剣殺という不安定化した状態に置かれる。一白は収縮の働きが基本であるが、三碧との関係性において気質を逆転させることがある。この場合血管収縮が血管拡張となるため血圧は下がる。震宮の一白は外界の刺激や環境条件に対して身体の状態を調整するため、血管平滑筋は収縮にも弛緩にも働く。このため不安定的に血圧が上下する。
〔利尿作用〕
カリウムにはナトリウムと水分を尿として排泄する作用がある。カリウムを多く含むミカンは利尿作用を促進する。三碧木星は一白水星(水分)の動きを促進する働きがある。利尿作用も発汗作用も震宮における一白水星の働きと考える。
〔低カリウム血症〕
低カリウム血症はカリウムの摂取不足、カリウムの体外への過剰排泄、血液から細胞内への移動が原因となって起こる。症状としては脱力、筋力低下、筋肉痛、呼吸障害、不整脈などがある。三碧木星の過不足は即一白水星の不安定化に繋がり、一白の不安定化は心拍、筋力、血流、腎機能、肝機能、ホルモン分泌、代謝に障害を及ぼす。低カルシウム血症は一白と三碧の連携不足および一白と六白の連携不足によってもたらされるものと考える。三碧と一白は常にバランスを保つ必要があり、いずれかの働きが過剰もしくは不足すると、三碧と一白の不調のみならず六白に関するマイナス症状も付随して現れる。
〔高カリウム血症〕
高カリウム血症の原因としてカリウム排出を妨げる薬剤、腎不全によるカリウム排出機能の不全などが掲げられる。高カリウム血症は筋肉、神経障害、尿毒症、尿路閉塞、腎石灰化症、腎炎、腎結石、不整脈、心臓機能の低下などを引き起こす。これらの症状も三碧木星と一白水星の関係性の不安定化として捉えることができる。暗剣殺とは五黄土星の対冲に現れる九星の不安定化したエネルギー状態であり、五黄の働きが両極に振れることに起因する。低カリウム血症と高カリウム血症は原因が異なるものの、九星の働きから見ると同じ三碧と一白、一白と六白の関係性の不安定化から生じるため、筋肉、心機能、腎機能の低下など同じ症状の傾向が現れる。
カリウムを多く含むスイカを食べすぎるとカリウム値が上昇し、腎機能や心機能に悪影響を及ぼすと指摘される。三碧木星の過剰は一白水星及び六白金星の臓器へ障害を及ぼす。
〔肥料〕
肥料の三大要素は窒素・リン酸・カリウムである。いずれの元素も三碧木星の成長促進の気質を持つ。
〔カリウム40〕
カリウムの同位体であるカリウム40は放射性物質である。我々の人体はカリウム40による自然界からの外部被ばくと食品からの内部被ばくを受けている。この場合カリウム40を三碧木星とし、自然放射線による人体への影響を震宮の一白水星と考える。天道を伴う一白水星暗剣殺はミトコンドリアを活性化させるカリウム40によるプラスの効用と考えることができる。
〔カリウムを多く含む食品〕
カリウムは大部分の食品に含まれる。昆布、ひじき、甘海苔、あおさ、青海苔などの藻類が最も多く、次いで緑茶、とうがらし・胡椒などの香辛料、大豆・小豆などの豆類、パセリ・ほうれん草・さといも・じゃがいも・スイカなどの野菜、バナナ・メロン・キウイフルーツ・梅干し・もも・柿・温州ミカン・ブドウなどの果実にも多く含まれる。
浅沼気学岡山鑑定所監修